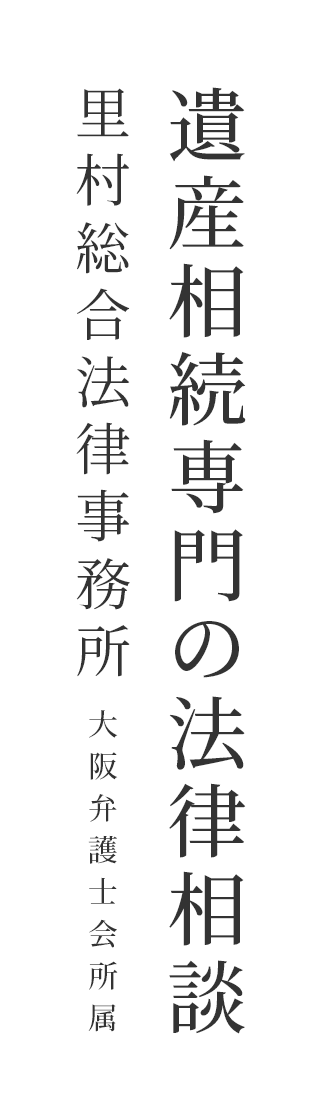遺言書を作成しておく

相続の場面では、「遺産分割協議」の際にトラブルが生じることがあります。
仕事柄よく伺う話が、「うちは子どもたちみんな仲がいいから、自分が死んだって揉めることはないですよ。」というような言葉です。しかし、当のお子様は、「父(あるいは母)はずっと自分たち子どもが小さい頃のままのイメージで話しますけど、いざ相続となったら絶対に揉めるんです」、などと、親と子の認識のずれが大きいことがままあります。
遺産分割協議となると、相続人全員が同意しなければならず、誰かがNOと言うと協議が成立しません。よくあるのは、自分は長兄だから財産を多く相続すべきである、とか、自分は最期まで親の近くで面倒を見たから財産を多く相続すべきである、といった主張がなされます。後者は、場合によっては寄与分という考え方によって認められる可能性がありますが、どの程度面倒を見たからいかほど多めに財産を相続できるか、いう点について、相続人全員で合意するのはなかなかに困難です。田舎の実家の土地建物は売るに売れないから自分は預貯金の方がよいなどとして、不動産の押し付け合いがなされることもよくあります。
以上から、遺言書を作成しておき、どの相続人がどの財産を取得するのかをあらかじめ指定しておいた方が絶対によいです、とアドバイスしています。特に、①相続財産に不動産が多数含まれる場合、②相続人間の関係性がよくないあるいは疎遠な場合はなおさらです。
相続人全員が足並みをそろえて合意を成立させるよりも、被相続人が自分の財産についてどのように相続してもらうか決めておく方が、はるかに手間と費用がかからず、また自分のことを自分で決めておくという意味で望ましいと考えます。加えて、人間は誰しも亡くなりますが、誰も亡くなった後の世界がどうなるかを知ることはできません。しかし、弁護士としては、その被相続人亡き後の世界を見て、遺言があればこういった問題は起こらなかったのに、と思うことがよくあります。
また、依頼者の方からよくされる話が、「自分はまだ元気だから、そんな遺言なんてまだ早い。」というものです。しかし、可能であれば今元気なうちに、自分亡き後のことを想定して、遺言を残しておいてほしいとも思います。遺言作成は一回作成したらそれっきり変更できないものではなく、後で考えや事情が変われば変更することもできます。
遺言を作成するとなった際に、どのような遺言を作るべきなのか、どのような遺言では問題となるのかについては、どういった内容の遺言を作成すべきか、というコラムで記載していますので、こちらもご確認ください。